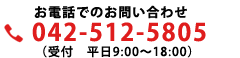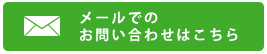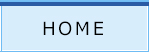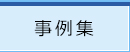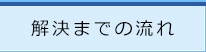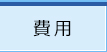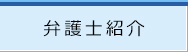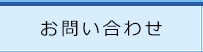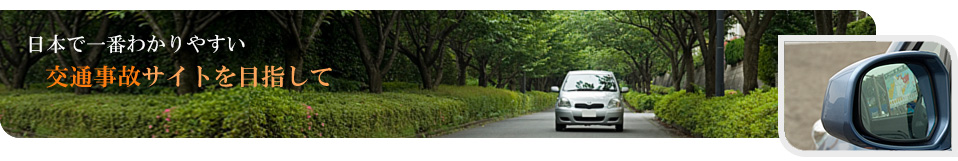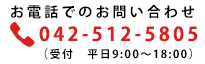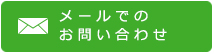有職者の休業損害の事例

休業損害とは事故のため休業した期間の損害のことで、サラリーマン、会社役員、自営業者など就業形態によって算定方法が異なります。
例えば、 交通事故でケガをして、後遺障害が認められた女性会社員の場合…
ケガの影響で作業に時間がかかってしまい、事故に遭う前のように仕事をすることができずに退職してしまいましたが、裁判で症状固定までの1594日間、1344万円余の休業損害を勝ち取ることができました。
給与所得者の休業損害
給与所得者の休業損害は、事故前の収入を基礎とし、受傷によって休業したことによる現実の収入減を算出します。現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。休業中に昇給・昇格があれば、その時点から昇給後の収入を基礎とします。また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。
認定例
運転手女性(48歳、右手小指RSD等14級)につき、月給月額32万円を基礎として、症状固定まで521日間555万円余を認めた(京都地判平16.3.24)
会社員男性(固定時32歳、一下肢を膝関節以上で失ったもの4級5号)につき、事故前年年収360万円余を基礎に、右足の切断の治療が社会復帰には一番早い方法であるとしても被害者が即断できなかったことを責めることはできず、事故は平成9年8月であるが切断手術が平成15年1月になったのもやむを得ないとして、症状固定までの2294日間合計2262万円余を認めた(神戸地判平17.11.1)
靴の貼工男性(66歳、右股関節の機能障害・右下肢の短縮障害・右小指の欠損障害等併合8級)につき、立ち仕事であることや傷害の内容・程度を勘案し、通院期間については逓減させるべきとの加害者の主張を排斥して、症状固定まで約4年2ヶ月の全期間1293万円余を認めた(神戸地判平19.5.24)
市役所の技能職員男性(事故時33歳、右足関節稼動域制限等併合10級)につき、有給休暇取得10日分、期末手当・勤勉手当の減額分、超過勤務不能分を認めた(大阪地判平20.3.14)
症状固定前に退職した事例
会社員男性(45歳、左股関節及び膝関節の機能障害等併合10級)につき、左股関節脱臼、左膝関節骨折などで症状固定まで5回の手術を受け6年(2216日)入通院し、その間勤務できないことから事故から約3年2ヵ月後に勤務先を解雇されたとして、解雇時の勤務先の昇給水準に依拠して症状固定までの見込まれる昇給を加味し、5350万円余を認めた)(札幌地判16.2.5)
会社員女性(事故時26歳、高次脳機能障害等併合6級)につき、アルバイトとして復帰したが、仕事(プログラマー)の内容について記憶を失っており作業時間がかかりすぎるために症状固定後に退職した場合に、事故前年の給与所得328万円余を基礎として、症状固定まで1594日間、復職中に得た収入を控除して1344万円余を認めた(名古屋地判平18.1.20)
事故後約1年9ヶ月後に左膝のタナ障害が発見されたカラオケボックス店員女性(固定時27歳、12級12号)につき、事故日から症状固定まで、職場一時復帰期間を除く671日間、449万円余を認めた(大阪地判平18.4.25)
水産会社勤務の会社員男性(33歳、頸椎破裂骨折・胸椎圧迫骨折に伴う脊柱変形等併合10級)につき、首の痛みのため早退が多くなり事故からの約1年9ヵ月後に退職した場合に、退職と事故との相当因果関係を認め、事故前の給与と賞与を基礎に症状固定まで928日間1028万円余を認めた(横浜地判平20.4.17)
派遣社員男性(29歳、右上肢のしびれ等12級13号)につき、事故後に休業したまま契約期間を満了したが、契約更新の制度があり、先行事故に遭う前は別の派遣先で4年以上継続して勤務していたことからすれば契約更新がされた蓋然性が高いとして、契約期間終了後も含め、日勤欠勤79日間分、夜勤欠勤65日分に早退分を加えて休業損害を算定した(大阪高判平20.11.5)
有給休暇
土木建設業会社部長の男性(58歳)の年次有給休暇(63日分)について、本来なら自分のために自由に使用できる日を事故による傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てたとして、休業損害算定の基礎日数とした(神戸地判平13.1.17)
自宅で静養するために合計13日の有給休暇を利用した場合につき、有給休暇の財産的価値に鑑み、前年給与所得を365日で割った金額で13日分を認めた(東京地判平14.8.30)
有給休暇1日当たりの金額に争いがある事案につき、賞与を除く年収を稼働日数(366日から勤務先所定の休日を差し引いた日数)で割った金額が相当であるとした(東京地判平18.10.11)
事業所得者の休業損害
客観的に所得が証明され、事故による減額が立証されれば休業損害が認められます。自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃、リース料、水道光熱費、損害保険料、従業員の給料等)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむをえないものは損害として認められます。
認定例
14級10号の理容師女性(固定時59歳)につき、事故直前まで1年間の合計収入を基礎に、事故日から症状固定まで右肩、頸部痛、右手の痺れ、腰痛、右膝痛が続いていたとして、全期間(328日)100%を認めた(岡山地判平11.12.20)
左官職人男性(固定時42歳、骨盤骨変形12級5号・右肩関節の可動域制限は非該当)につき、右肩の機能や筋力回復の必要、作業の安全性等の事情を考慮して、症状固定まで660日間100%を認めた(東京地判平13.5.29)
映像コンテンツの企画、演出等の業務を行っていた事業所得者につき、事故による疼痛でDVD制作のためのロケハン、シナリオ台本作成等を予定時期までにできず制作会社との間の契約を解除されたとして、得られなかった出演料1200万円から支払を免れた打合わせ費用120万円を控除した1080万円のほか、得られなかった著作権料30万円、損害賠償を求められたロケハン等費用48万円余を損害として認めた(東京地判平18.7.19)
申告所得を超える収入を認めた事例
事業所得者の場合、どれくらい収入があるかの証明について税務申告の金額が客観的資料として利用されます。しかし申告所得を超える金額を収入として認めた事例もあります。
電気工事事業者男性(54歳)につき、確定申告額は100万円余であったが、事故前の収入及び経費について、主な受注先への売り上げが640万円あって経費が93万円と認められるとして、年額550万円を基礎とした(大阪地判平13.2.15)
日給制の塗装工男性(固定時63歳)につき、税務申告上は個人事業者として架空の経費(経費率は事故の前年は約57%、事故年は66%)を控除して申告していたが、実際の経費は通信費及び消耗品程度であることから経費率を5%程度と認め、これを事故前年の年収から控除した573万円余を基礎とした(大阪地判平15.12.24)
減収はないが休業損害を認めた事例
休業をしたけれど、減収は無かった場合でも休業損害が認められる場合があります。
妻の協力により減収のない建築工事業代表者につき、賃金センサス男性学歴計35歳から39歳平均を基礎として、入院中は100%、その後の1年間は50%、その後症状固定まで133日間は20%の労働能力制限を認めた(大阪地判平9.3.25)
不動産鑑定士の男性(43歳、14級10号)につき、事故後に所得が増加しているが、仕事量を増やすことができないまま事故前に受注した仕事をしていたことを考慮し、事故前年の所得を基礎に、症状固定まで202日間、平均2割労働能力を喪失したとして、182万円余を認めた(東京地判平18.10.30)
固定経費に関する事例
休業中にもかかってしまう家賃、リース料、水道光熱費、従業員の給料などの固定経費についても賠償の対象となります。
喫茶店経営者につき、店舗家賃、駐車場、光熱費、自動車保険料、火災保険料、自動車税、個人事業税の支払額を認めた(大阪地判平11.11.9)
極めて優秀な業績をあげていた生命保険外務員の女性(42歳)につき、事故前の2年間の平均年収1367万円余に、休業中も支出を余儀なくされた通信費、接待交際費及び諸経費の合計486万円余を固定経費として加算したものを基礎に、315日間合計1599万円余を認めた(京都地判平14.5.23)
事業再開後の損害に関する事例
歯科医の男性につき、事故による入院療養のため、その経営する歯科医院を3ヶ月休業した場合に、休業期間の所得減少に加え、診療再開後も休診の影響から患者が減少し売上が減少したことから、診療再開後3ヶ月間の売上減少の8割を損害と認めた(名古屋地判平14.9.27)
廃業による損害に関する事例
事故後廃業した美容院経営者の女性(50歳)につき、事故に遭わなければ美容院の経営を継続していたことが推認されるとして、事故から約2年前の開業時に支出した費用564万円余の約5割を認めた(高松高判平13.3.23)
間接被害者に関する事例
事故により受傷した被害者の父母につき、その経営する浴場を休業した場合に、確定申告の年収をもとに休業損害を認めた(大阪地判平5.9.6)
事故により死亡した被害者女性(80歳)の次女(ジャーナリスト、出版物・テレビ番組等の企画・編集)につき、葬儀などを行うために雑誌記事の休筆や執筆者を交代せざるを得なかった場合に次女が経営する会社の減収分もその実質は次女個人の損害と評価し得るとし、事故直後の期間(1、2週間)に限って事故と相当因果関係があるとして、393万円余を次女固有の損害と認めた(東京地判平17.6.21
代表者が受傷した航空測量会社につき、事故前年は赤字であるが、技術者が代表者1名、従業員は2名で、航空測量には技術者が必要で技術者抜きでは営業も成り立たないとして、事故による現実の売上の減少があることなどから、民事訴訟法248条により口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を総合し、代表者の役員報酬減収分の休業損害と別に、会社の休業損害250万円を認めた(名古屋地判平20.12.10)
代替労働力に関する事例
新聞販売店舗経営男性(38歳)につき、事故のため被害者が新聞配達を行えなかった期間、代行の新聞配達要員に支払った派遣料を認めた(大阪地判平11.8.31)
一人で開業している歯科医師女性(39歳)につき、一人で全患者に対する診療行為を行うことができなくなった場合に、一部代診を依頼した医師に対する38日分の給与335万円余を認めた(横浜地判平15.3.7)
会社役員の休業損害
会社役員の場合、従業員と異なって、仕事を休んだからといって直ちに給与が減額されるわけではありません。役員報酬の中には、労働の対価として支払われる部分と利益配当の実質をもつ部分があり、仕事を休んだことによって失われるのは、労働対価の部分のみとなります。 例えば、従業員が少なく、いわゆるワンマン会社でその役員が営業の先頭に立って営業活動を行っている場合は、役員報酬のほとんどの部分が労働対価の部分として評価できます。
建物解体工事・建材卸業等を目的とする会社の代表者につき、個人会社で被害者の職務内容も肉体労働が多いこと等から、月額100万円の役員報酬全額を労務の対価と認めた(千葉地判平6.2.22)
鉄工業を目的とする会社の代表者(高卒男性・固定時62歳)につき、会社は事故当時営業損失を出していたが、年間1200万円の役員報酬が支払われていたこと、賃金センサス、他の役員報酬や従業員の賃金との比較等を併せ考えて役員報酬の7割、840万円を労務の対価と認めた(東京地判平11.10.20)
父親の経営する印刷会社の監査役男性(30歳)につき、会社の中心的な働き手として稼動していることから、会社から得る収入はその労務の対価として不相当ではないとして、事故前年収全額を基礎とした(東京地判平13.2.16)
印刷会社の専務取締役男性(固定時57歳)につき、会社の規模(社員7名)・利益状況(事故後の次期に売上高が減少し、営業損失を計上)に加え、被害者が実質的な営業活動をしていたこと、事故後の役員報酬の減収状況、学歴等に照らし、控えめに見ても役員報酬のうち労務対価性のある部分は月額130万円の70%、91万円を下らないとして、実際に支給を受けた額を控除して症状固定まで18ヶ月分、738万円を認めた(東京地判平17.1.17)